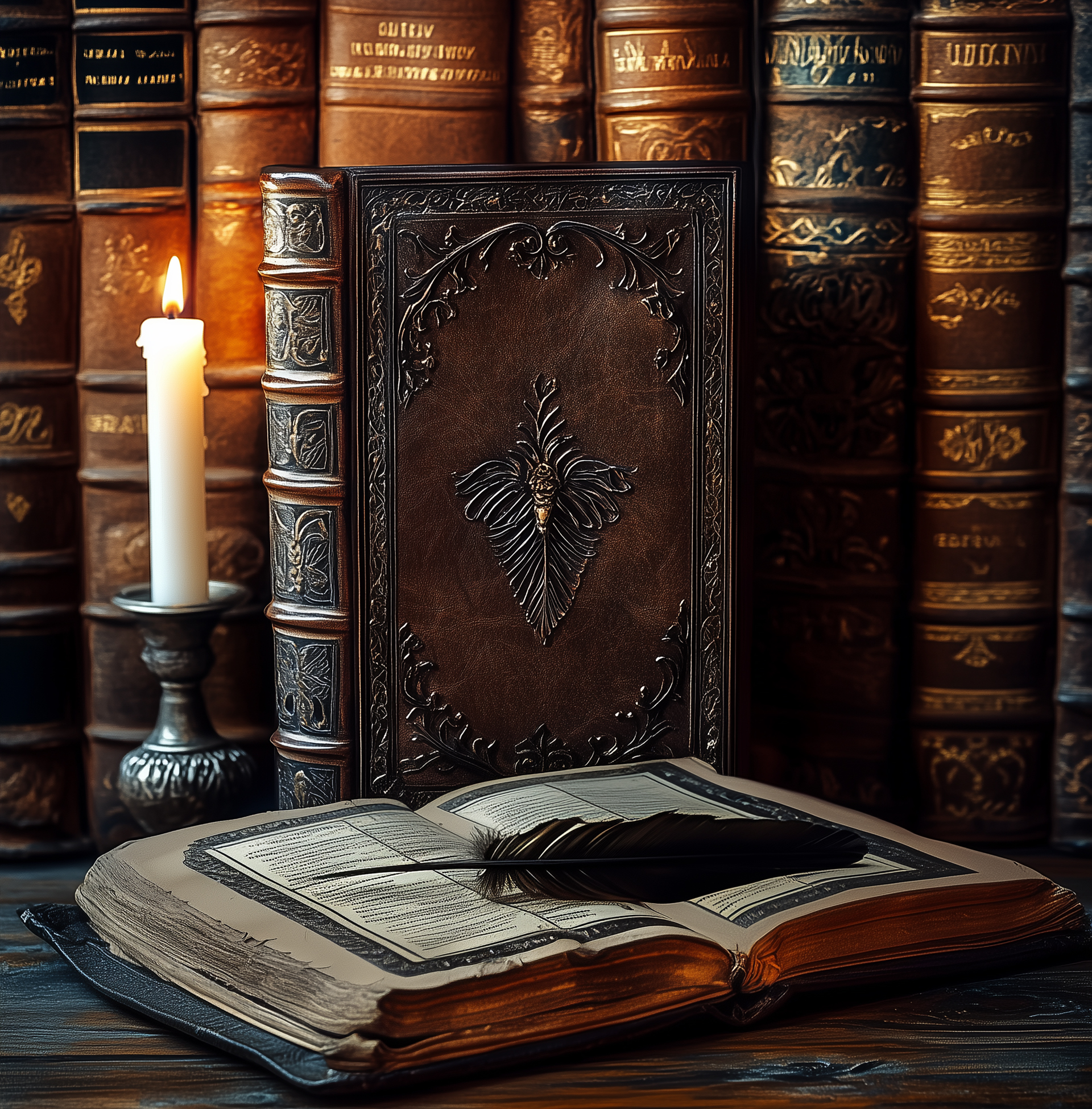
和製英語は曲者揃い
実は紫乃女は英文学科出身です。
昔から英語が得意だったわけではありません。中学の頃は逆に苦手科目でした。
中二の頃なんかもう「何がわからないのかわからない」という末期的な状態で、英語の先生が匙を木星あたりまでぶん投げそうな惨憺たる(さんさんたる=めっちゃひどい)成績だったんです。
まず、なぜ三人称単数の時にdoがdoesに変化するのかが理解出来ない。代動詞(助動詞)風情が幅を利かせすぎ!「彼」と「彼女」の時はdoesになるくせに、複数になったとたん(theyとかyouとか)doに戻ったりするじゃないですかあいつ。
しかも比較級がさらに意味がわからない。
fast → faster → fastest みたいに語尾に-erと-estつければいいのかと思ってたら、2音節以上の単語だとbeautiful → more beautifulみたいになるってどういうこと?そしてもっと許せないのが、good → better → best と bad → worse → worst。変化が不規則すぎでしょ?手に負えない!
中二のあたしはこの不満を英語の先生にぶつけました。
英語を学ぼうと日々努力はしているが、相手のタチが悪すぎるのだと。
何から手をつけたらいいのかすらももう分からなくなってしまったんだと、あたしは必死に訴えました。

先生の答えは実にシンプルでした。
「チェスで遊びたければ、まずチェスのルールを覚えるでしょう?
それがどんなに複雑怪奇であっても、あなたは黙ってルールを覚えようとするはずです。
ビショップの駒は斜めに動く、ルークの駒は縦横に動く。
キングは1歩だけだけど、八方向全方位に動ける。
ややこしいルールですが、あなたは文句も言わずに覚えようとするでしょう。
英語も同じです。上達したければまずは基礎のルールを覚えなさい。
ルールに「なぜ」も「どうして」も不要です。それが「ルール」というものです。
ルールを覚えぬ者に上達の道はありません。」
あたしは何も言い返せませんでした。
同時に、この人が自分の先生であることをとてもありがたく思いました。
あたしは学校で支給されている「マスター英文法」という分厚い本を抱えて家路につきました。
その日を境として、あたしの英語の成績は上がり始めました。
英語はあたしにとって「好きではないけれど点数の稼ぎやすい」科目となりました。
先生の言葉は正しかったのです。
しかし、英語を学べば学ぶほど、
日本語の中に堂々と紛れ込む『和製英語』の存在が気になり始めました。
良く言えば「英語の顔をしているくせに日本語の心を持っているデーブ・スペクターさんみたいな存在」、悪く言えば「ひとたび海外に連れ出すと全然通じない曲者」であるあの連中です。お前を信じて外人さんの前で使ったのに「え?」みたいな顔をされるこっちの立場もちったぁ考えろというんだ!(ノ*`´)ノ⌒┻━┻
今回はそんな「曲者:和製英語」について少しお話しようかと思います。
まず、みんな大好き食べ物編から。
日本の「オムライス」、あれはフランス語の omelette(オムレツ)と英語の rice(ご飯)を合体させた、日本発の混成語です。もはや和製英語ですらない。和製英語フランス語だよ。
海外でも “omurice” という日本料理名として通じるお店が増えてきたけれど、一般的な英会話ではまだ「?」なこともあります。メニューに “omelet rice” と書くお店も増えてはきていますが、定着度は国と店による、そんな立ち位置です。

そして、永遠の課題「シュークリーム」。
日本語の「シュー」は英語の shoe(靴)じゃなくて、フランス語の chou が由来です。丸い生地がキャベツ(=chou)に似ているからそう呼ばれたんですが、これ、英語圏だと「靴のクリーム(靴墨)」になっちゃうんじゃないかってちょっとひやひやしますよ。ま、普通、靴墨は英語ではshoe polishっていうので「シュークリーム下さい」って言って靴墨を渡される哀しい事故は防げるとは思いますが。
(shoe creamと綴った場合はOUT。おとなしく靴墨を受け取って下さい)
ちなみに「シュークリーム」は英語圏では cream puff が一般的で、小粒でチョコがけだったりアイスが入ってたりするタイプなら profiterole と呼ぶこともあります。カロリーやばそう(´・_・`)
食卓から離れて、生活語に話を移しましょう。
日本で当たり前の「マンション」は、英語の mansion が意味する「大邸宅」とは違います。
海外の友だちに「I live in a mansion.」とか言うと、一瞬でセレブに化けることになるので注意が必要です。ふつうは apartment(賃貸)か condominium(分譲)で十分でしょう。超セレブな方々は安心して「I live in a mansion!」と叫んで頂いて大丈夫ですよ(´・_・`)b
それから「クレーム」は英語の claim(主張・請求)から来ていますが、日本語の「苦情」の意味を正しく伝えるなら complaint が正解です。
「サービスです(無料です)」は complimentary とか on the house が自然です。
service だけだと「接客」全般の話に見えることが多いので注意しましょう。
(※on the house=お店側が負担しますよ・お代は結構ですよ の意味)
ホテルで「モーニングコールお願いします」は、英語だと wake-up callになります。
ライブ小屋の「ライブハウス」は live music venue や club。
ベビーカーは stroller(米)か pram(英)。
あと、これは地味に大事なんですが、「ドライヤー」ね。
英語で dryer は文脈によっては衣類乾燥機のことを指すことが多いので、髪の方は hair dryer と明示すると誤解が減ります。
(ドライヤー貸してほしいんですがと頼みに行って乾燥機が置いてある部屋に案内されたらちょっとむなしくなりません?「ヘア」をつけるだけでそんな事故は防げます)
まだまだありますよ。
コンビニで買った飲み物の「サイダー」は、英語の cider と同じじゃありません。
アメリカだと cider はリンゴ果汁(地域によっては非炭酸・非アルコール、アルコール入りは hard cider)、イギリスだと基本アルコール入りです。
日本の透明な炭酸が欲しけりゃ soda か、むしろ商品名で指定したほうが安全ですね。
(わりとよく見かけるのが Perrier、ペリエね。Natural か Original って指定すれば無糖タイプが手に入ります。逆に、日本でメジャーな Wilkinson ウィルキンソンですが、実はアレ、アサヒ飲料が出しているやつなので海外ではあまり見かけません)

ビジネスの現場も和製英語の宝庫です。
「リスケ」は reschedule、「コスパ」は value for money や cost-effectiveness。
メールで「NGです」は日本では通じても、英語の “NG” は一般的ではないから not acceptable とか won’t work など文脈に合わせて言い換えたほうが良いでしょう。
(NGって何の略?って不思議そうに聞かれたりしますよ。NO GOODの略じゃん!傷つくわぁー)
「タレント」は TV personality や celebrity、「マスコミ」は the media。どれも英語っぽい顔をしてるけど、英語圏の耳にはちょっと違って聞こえるみたいですね。
家の中を見回しても、和製英語のクセはそこらじゅうに転がっています。
「コンセントに挿して」と言うけれど、英語は outlet や socket。語源は「同心円(concentric)型プラグ」周辺の呼称が縮んで一般化した、という説明がよく紹介されていますが、ここは“諸説あり”と覚えておきましょう。「諸説あり」ってホントに便利な言葉ですよね!ヾ(´▽`)ノ
文房具だと「ホッチキス」は Hotchkiss 社の商標が日本語の一般名になった経緯が有名で、英語では stapler。「シャーペン」は Sharp(メーカー名)の成功で定着した呼び名で、英語は mechanical pencil。キッチンに置いてある「レンジ」は microwave oven(マイクロ波の方)か stove/range(ガス台・コンロ)かで意味が割れるので、ここも具体的に言ったほうが親切でしょう。
服装の話もしておきましょうか。
「ノースリーブ」は日本語としては完全に定着していますけれど、英語で no-sleeve とはあまり言わないんです。sleeveless top や tank top のほうがしっくり来ますね。
冬に巻く「マフラー」は英語だとふつう scarf。muffler も間違いではないけど、今はやや古風か地域限定の響きになることがあるので要注意です。
それから、思わず言いがちな「センスがいい」は good taste。good sense だと「判断力が良い」寄りに伝わるので、ファッションや趣味の話なら taste を使うと安心です。
スポーツやしぐさ系だと、「ガッツポーズ」も日本ならでは。英語なら fist pump や victory pose が状況に合います。だって「ガッツ」って内臓のことだよ?guts poseって「臓物を見せつけるポーズ」ってことじゃないですか。ホラー映画じゃないんだから(´・_・`)
ちなみに、日本で「バイキング」と言えば食べ放題のことですが、英語で Viking はもちろん“北方の海の人たち”のことです。食べ放題は buffet と言います。
(これは豆知識ですが、なぜ日本では食べ放題のことをバイキングと呼ぶようになったかと申しますと、昭和30年代に、帝国ホテルさんが、デンマークの首都コペンハーゲンにあるレストラン「スモーガスボード」の食べ放題な食事形式を日本でも取り入れようと試みた際、「スモーガスボード」という言葉があまりにも日本に馴染みが無さすぎるということで、北欧全体で親しまれている食事形式「スモーガスボード」→ ちょうどその頃日本で大ヒットしていた『バイキング』という映画は北欧の海賊の物語だ → じゃあ北欧繋がりで食べ放題の食事形式を「バイキング」と名付けちゃえ!という結構大胆な命名のせいなんです。当時の帝国ホテルの方々に「なんぼなんでも無理があるんじゃないか?」と小一時間ほど問いただしたい紫乃女ですよ)
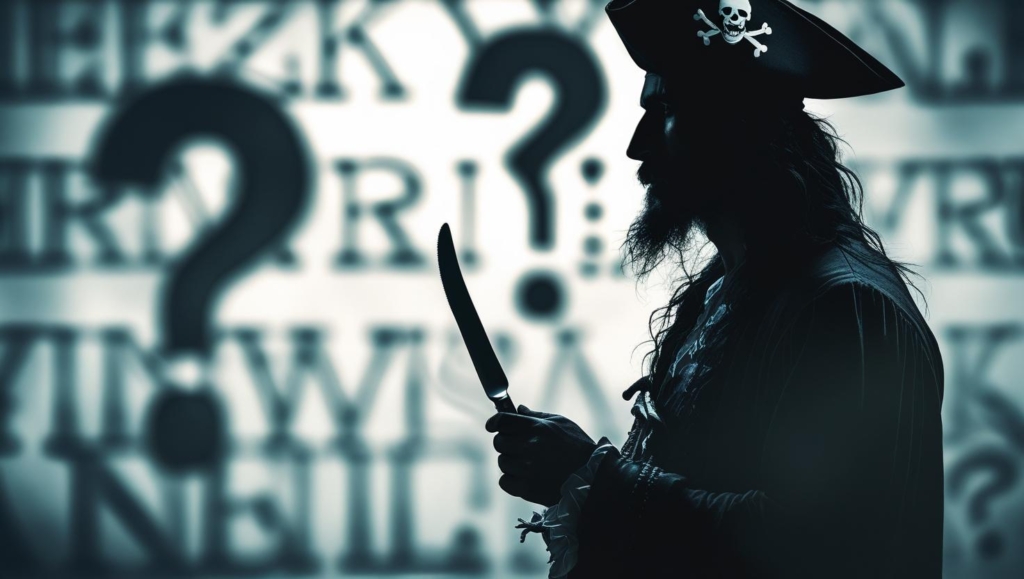
あと、日本でも死語になりかけている「コンパ」は mixer や get-together、会社員の「サラリーマン」は office worker や salaried employee。女性にだけ「OL」という呼び方をするのは、英語でも日本語でもだんだん時代遅れになってきているので、ニュートラルな肩書に寄せたほうがいいでしょう。
ね、和製英語ってつくづく曲者でしょう?日本語のなかではのびのび育って、海外に出るとちょっと内弁慶が顔を出す、そんな感じです。だからこそ、私たち話し手のほうが一歩だけ歩み寄って、相手に合わせて言い換えてあげればいい。それだけで会話はするっと滑らかになるものです。和製英語も国際英語も、どっちが正しいかじゃなくて、どっちが今この瞬間の相手に親切か。そんな視点で、今日も気楽にやっていきましょう。Let’s get more familiar with that damned English language!(あのクソ忌々しい英語にもっと慣れ親しもうじゃないか!)
